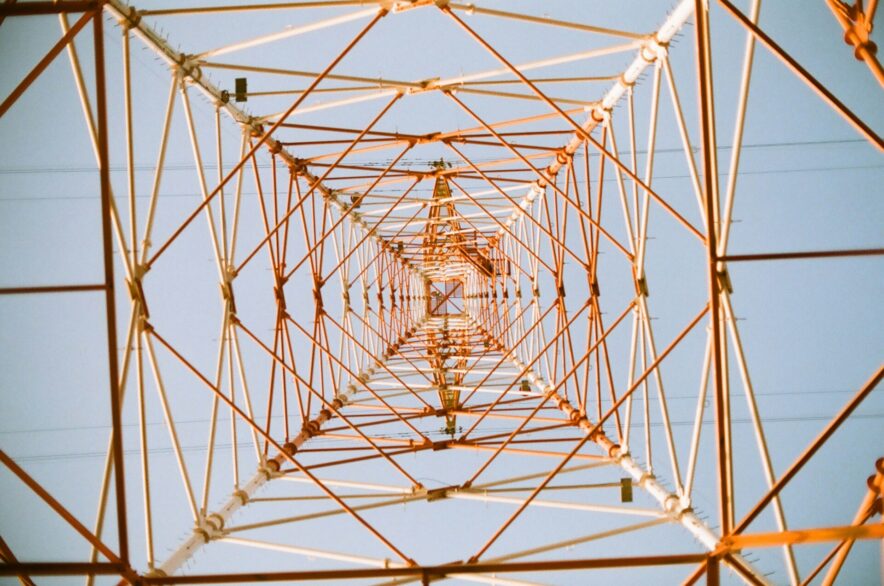Efficiency and Breath — When Optimization Begins to Narrow Life
前章では、
世界が誰かの意思によって動いているわけではなく、
意図を持たない構造が、生の条件を静かに形づくっていることを見てきた。
構造は、意図を持たずに働く。
その中で、いつのまにか当たり前になっていった価値がある。
効率である。
効率化。最適化。合理性。
それらは本来、私たちの生活を楽にするための概念だった。
時間を短縮し、無駄を減らし、
より少ない負荷で同じ成果を得る。
それ自体は、否定されるべきものではない。
効率がもたらした豊かさ
効率という思想によって、
私たちの生活は確かに多くの恩恵を受けてきた。
移動は速くなり、
情報は瞬時に届き、
選択肢は画面の中に整然と並ぶ。
かつて多くの時間と労力を要していた行為は、
いまではわずかな操作で完了する。
効率は、自由な時間を生み出すはずだった。
よりよく生きるための余白を、
私たちに与えるはずのものだった。
しかし、どこかで感覚がずれはじめる。
最適化が「基準」になるとき
効率が手段ではなく、
基準そのものになったとき、
世界の風景は少しずつ変わっていく。
速いことが良い。
成果が明確であることが正しい。
測定できるものが評価に値する。
こうした前提が、
静かに日常の隅々まで浸透していく。
やがて私たちは、
「どれだけ感じたか」よりも、
「どれだけ達成したか」を問われるようになる。
過程よりも結果。
揺らぎよりも安定。
迷いよりも即断。
それらが、無言の標準になっていく。
それは、世界が冷たくなったからではない。
ただ、生命のリズムが受け取られにくくなっただけなのかもしれない。
感じることと、動くことの分離
このとき、ひとつの断絶が生じる。
感じることと、動くことが、
同じ場所から発していなくなる。
身体がまだ納得していないのに、
思考だけが先に結論を出す。
違和感が残っているのに、
合理的だからという理由で進んでしまう。
それは意識的な裏切りというより、
そうする方が「正しい」と教えられてきた結果でもある。
効率の論理は、
感覚を誤りとして扱いやすい。
測れないもの。
言葉にならないもの。
理由を説明できない躊躇。
それらは、しばしばノイズとして処理される。
効率が判断の速度を求めるほど、
身体の応答は、待たれなくなる。
壊れてはいないが、痩せていく感覚
この社会は、どこか壊れているわけではない。
機能している。
回っている。
成果も出ている。
それでも、人の内側で、
少しずつ痩せていく感覚が生まれることがある。
理由は明確ではない。
不満として言語化できるほど強くもない。
ただ、呼吸が浅くなるような感覚。
選択肢が多いはずなのに、
どこか身動きが取りづらい感じ。
それは、個人の弱さというより、
構造と生命のリズムのずれから生じている可能性がある。
生命の時間と、社会の時間
生命は、本来、一定の速度では進まない。
揺れ、滞り、立ち止まり、
ときに遠回りしながら応答していく。
一方で、社会の時間は、
一定のテンポを保つことを求める。
止まらないこと。
遅れないこと。
常に更新され続けること。
このふたつの時間が重なったとき、
摩擦が生まれる。
その摩擦が、
生きづらさとしてではなく、
言葉にならない「息苦しさ」として現れることがある。
次章へ
効率の問題は、
善悪の対立として語れるものではない。
それは、便利さと引き換えに、
どのような配置が生まれてしまったのかという問いである。
次章では、
こうした構造の中で、なぜ世界が人を均等には扱わないのか、
その現れ方について見ていく。
努力や意志では埋まらない差が、
どこから生じてくるのかへと、視線を進めていく。
深層シリーズ 第Ⅱ部 記事一覧
第Ⅱ部では、生命が立たされている
「世界の側」に、そっと視線を移していきます。