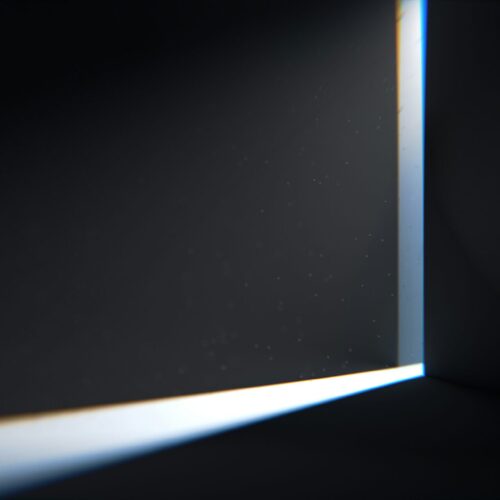Moving Forward While Holding Contradiction
私たちの毎日は、安定を求める気持ちと、変化を受け入れる必要のあいだで揺れ続けている。
生命の視点に立てば、「安全で驚きの少ない世界」(安定)と、「未知から学びを得る世界」(変化)の両方が、生き延びるために欠かせない。
その二つを同時に抱え、歩を進める姿勢――それがAPLFにおける「原則1:矛盾を抱いて進む」である。
目次
原則の核心 ─ 定義と要点
- 矛盾やゆらぎを排除しない。 白黒を急がず、濃淡(グラデーション)を見つめる。
- 「どちらか」ではなく「どちらも」。 安定と変化、計画と偶然、直感と論理を併置する。
- 判断の軸は“自分の律”。 揺れの中心に戻れる基準(価値観・習慣)を育てる。
短く言えば、矛盾を抱えたまま前に進む力である。完全な整合を待つのではなく、歩みの中で整えていく。
いま起きている矛盾の例
- スピードを求められながら、丁寧な関係づくりも必要である。
- 遠隔でつながりやすくなったからこそ、身体の感覚をどう保つかが問われている。
- 合理を重んじながら、遊びや余白からしか生まれない価値もある。
これらは「どちらが正しいか」ではなく、行き来しながら適切な“間”を探るテーマである。
実践 ─ 日常に落とすための手がかり
1)ミクロ:1日の中で“行き来”をつくる
- 深く集中する時間と、意図的に解放する時間(散歩・伸び・無目的)をセットで計画する。
- 意思決定では、「100%信じ、100%疑う」の両視点で一度だけ見直す。
2)メゾ:基準(律)と環境(整え)を育てる
- 価値観・行動基準・禁止事項よりも「こう在りたい」を短文で言語化しておく。
- 光・音・香り・姿勢など、戻れる環境のスイッチを用意する(お気に入りのノート、音楽、椅子など)。
3)マクロ:矛盾を設計に織り込む
- プロジェクトに「検証と余白」を最初から組み込む(例:2週間に1回の再設計タイム)。
- 関係づくりは、オンライン×オフラインの二層で構築する。どちらにも偏らない。
この原則を示す代表タグ
#live_with_paradox(矛盾を抱いて進む)
─ 矛盾やゆらぎを抱えたまま進む姿勢を示す代表タグ。
この原則は、ひとつの結論として閉じるためのものではない。
APLFの文章や実践、選び方や語り口の随所に、前提として滲み出ている姿勢である。
特定の記事に集約されるというより、複数の体験や視点のあいだに、静かに現れている。
関連リンク
この原則は、以下の記事群と強く響き合う。
- 特集:感性の三部作

Appreciate Life through Wine 食からはじまり、空間を経て、ワインへ。 半年の学びのなかで、「味わう」という行為は、 ただの感覚ではなく、世界の構造を映す鏡となっていった。 一皿の背景にある人や物語、 空間がつくる味わいの重なり、 そして、ワインという言...

Appreciate Life through Choice よいものを選ぶというのは、単に品質を見極めることではない。 それは、世界をどのように感じ、どう関わるかという「姿勢」を選ぶ行為でもある。 味わいが感性の行為だとすれば、選択はその感性の延長線上にある。 何を美しいと感じ...
詩的な感性の面から同テーマを綴ったエッセイも、noteで公開している。
note「味わい・よいもの・驚き」シリーズ
APLFの7つの共通原則|記事一覧
APLFの思想を形づくる7つの共通原則を、一覧から横断して読むことができます。