The World Emerges from How You Cut It
同じ世界を見ていても、誰もが少しずつ違う景色を見ている。
自分がどこに立ち、どの角度から世界を切り取るかで、意味も価値も変わる。
「自分の断面で世界を切る」とは、他人の正解ではなく、自分の視点から世界を構築していく姿勢のことだ。
この原則は、感性や知性を超えて、「どこから世界を見ているか」を問うものである。
その切り取り方こそが、自分の思考・創造・生き方の“型”になる。
目次
原則の核心 ─ 自分の視点で世界を再構築する
他人の価値観をなぞるのではなく、自分の感受性・経験・信念に基づいて世界を編集する。
それが「自分の断面で世界を切る」ということだ。
見方を変えることは、世界を変えること。断面を意識することは、主体的に世界と関わることでもある。
断面は固定されたものではなく、状況や成長に応じて変化する。
むしろ、断面を自在に切り替えられる柔軟性こそが、現代における知の成熟である。
生命の観点から見る「断面」
生命は環境の一部を切り取り、情報として処理しながら生きている。
感覚器官も、思考も、感情も、世界の“断面”を抽出しているにすぎない。
つまり私たちは、世界そのものを知っているのではなく、世界の断面を生きているのだ。
だからこそ、どの断面を選び、どの断面を磨くかが、その人の生の輪郭を決めていく。
現代の課題 ─ 他人の断面に引きずられる時代
- SNSでの情報や評価が、自分の感受性よりも強く働いてしまう。
- 「正解」を求めすぎて、自分の軸で世界を見る力が弱まる。
- 他人のフレームに従って動くうちに、自己の断面が曇ってくる。
こうした時代において、「どの断面で世界を見るか」を再確認することは、
個の回復であり、感性のリセットでもある。
実践 ─ 自分の断面を見つけ、育て、使い分ける
① 感情を手がかりに断面を知る
最近、心が動いた瞬間を3つ挙げてみる。
それは「怒り」「安堵」「感動」など、感情の揺れでも構わない。
そこには、自分が世界をどの断面で感じているかのヒントが隠れている。
(例:構造の美しさ/人との関係性/時間の流れ/静けさの質)
② 観察の角度を変えてみる
ひとつの対象を、違う断面で3回観察してみる。
「機能の断面」「情緒の断面」「構造の断面」など。
断面を意識的に変えることで、ものの見え方が立体化する。
③ 断面を共有する
自分の断面を言語化し、人と共有してみる。
それだけで、他者の断面との重なりやズレが見え、対話が豊かになる。
世界を語るとは、断面を交換することなのだ。
この原則を示す代表タグ
#stand_in_perspective(私だけの視点)
─ 自分の視点で世界を切り取り、意味を見いだす姿勢を示す代表タグ。
「自分の断面で世界を切る」とは、自己中心ではなく、自覚的に関わる姿勢である。
どの断面から世界を見るかを意識することは、同時にその断面を育てるという行為でもある。
世界は自分の断面を通して更新され、自分自身もその中で変化し続けていくのだ。
関連:よいものを選ぶとは、世界の見方を選ぶこと

Appreciate Life through Choice よいものを選ぶというのは、単に品質を見極めることではない。 それは、世界をどのように感じ、どう関わるかという「姿勢」を選ぶ行為でもある。 味わいが感性の行為だとすれば、選択はその感性の延長線上にある。 何を美しいと感じ...
関連:驚きという構造 ― 世界がひらく瞬間
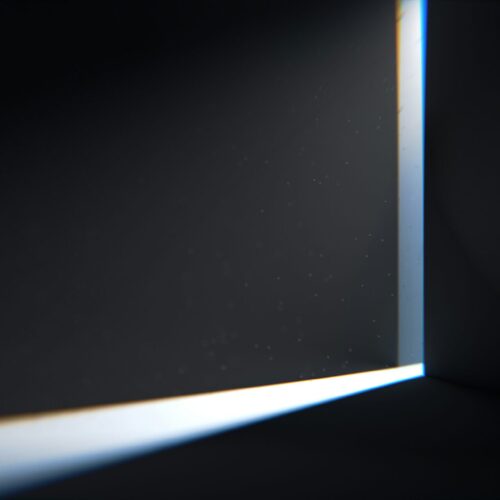
Appreciate Life through Wonder 世界はいつも、私たちの知覚の枠組みの中で見えている。 見慣れた道、聞き慣れた声、繰り返される習慣。 その安定の上に、私たちは世界を“理解した”つもりで立っている。 だが、ある瞬間、予期せぬ出来事や、何気ない風景のなかで、 ...
詩的な感性の面から同テーマを綴ったエッセイも、noteで公開している。
note「感性の三部作」
APLFの7つの共通原則|記事一覧
APLFの思想を形づくる7つの共通原則を、一覧から横断して読むことができます。