Letting the Body Sense Before Words Appear
私たちは日々、思考と言葉の中で生きている。
けれど、世界を最初に受け取るのは、思考ではなく身体である。
風の匂い、肌の温度、他者の気配。
それらが、言葉になる前に世界とのつながりを教えてくれる。
「身体と感性をひらく」とは、考える前に感じることを取り戻すということだ。
感性の回路を開くことは、生きる知覚を取り戻すことでもある。
目次
原則の核心 ─ 言葉よりも先にある知
感性とは、情報ではなく「反応」のことだ。
触れた瞬間に、身体がどう動き、どう感じるか。
そのわずかな反応が、世界と自分をつなぐ最初の会話になる。
理性が世界を整理するなら、感性は世界を感じさせてくれる。
どちらも大切だが、現代の私たちは思考の側に偏りすぎている。
だからこそ、いま改めて「感じる力」を取り戻すことが必要である。
生命の観点 ─ 感性は生存のための知
動物たちは、匂いや気配、音の揺れで世界を感じ取り、生き延びている。
感性は、思考よりも古く、生命が世界とやりとりするための原初の知だった。
人間もまた、感性を通して世界の変化を読み取り、自らを調整してきた。
つまり、感性とは生命の「予測と応答の技術」である。
世界の揺らぎに耳を澄ませ、自分の内側と外側を一致させていく。
その営みが「生きる」ということそのものである。
現代の課題 ─ 感性の鈍化と情報の過多
- デジタル情報があふれ、五感を通さない世界体験が増えている。
- 常に「判断」や「効率」を求められ、感じる余白が失われている。
- 身体の声よりも、頭の中のノイズを優先してしまう。
感性が閉じてしまうと、世界との関係が平板になり、生の実感が薄れていく。
いまこそ、「感じること」を日常の中で取り戻すことが求められている。
実践 ─ 感性をひらく3つのステップ
① 感覚を言葉にしないまま味わう
朝起きたときの空気、夕方の光、手に触れる器の重さ。
「きれい」「心地いい」とラベルを貼らず、ただ感じる時間をもってみる。
言葉を挟まないことで、世界と直接つながる感覚が戻ってくる。
② 身体の“重心”を感じる
考えすぎているとき、身体の重心は頭や胸のあたりにある。
深呼吸をして、重心を「下腹(丹田)」に戻してみる。
世界の重さを受け止める身体の安定軸ができ、思考も静まる。
③ 自然と対話する
風、木、水の音、空の色。自然はいつも、沈黙の言葉で語りかけている。
毎日数分でも自然と触れ合う時間を持つことで、身体の感度が再調整される。
感性は磨くものではなく、思い出すものだ。
この原則を示す代表タグ
#sense_before_words(感覚が先、言葉はあと)
─ 言葉になる前の感覚を大切にする姿勢を示す代表タグ。
感性をひらくことは、自分と世界の関係を更新することだ。
思考が世界を「分ける」なら、感性は世界を「つなぐ」。
感じる力を取り戻すことは、再び世界に触れることでもあり、
生命としての自分を取り戻すことでもある。
関連:味わいの構造 ― 食からワインへ、学びの旅路

Appreciate Life through Wine 食からはじまり、空間を経て、ワインへ。 半年の学びのなかで、「味わう」という行為は、 ただの感覚ではなく、世界の構造を映す鏡となっていった。 一皿の背景にある人や物語、 空間がつくる味わいの重なり、 そして、ワインという言...
関連:驚きという構造 ― 世界がひらく瞬間
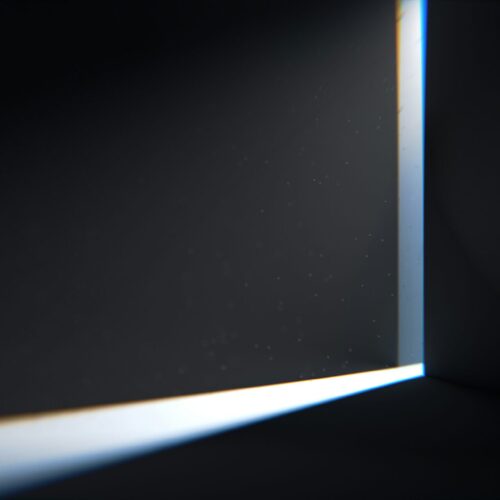
Appreciate Life through Wonder 世界はいつも、私たちの知覚の枠組みの中で見えている。 見慣れた道、聞き慣れた声、繰り返される習慣。 その安定の上に、私たちは世界を“理解した”つもりで立っている。 だが、ある瞬間、予期せぬ出来事や、何気ない風景のなかで、 ...
詩的な感性の面から同テーマを綴ったエッセイも、noteで公開している。
note「感性の三部作」
APLFの7つの共通原則|記事一覧
APLFの思想を形づくる7つの共通原則を、一覧から横断して読むことができます。