この特集は、APLFの「生命の動き(感性・哲学・実践)」のうち、感性の呼吸をたどる連作です。
食からはじまり、空間を経て、ワインへ。
「味わう」という行為を通して、感性が“受け取る力”を取り戻していく。
そこから「よいものを選ぶ」「驚きに開く」へと世界が広がっていく──
感じること、選ぶこと、そして再び世界と出会い直す三つの記録。
感性という呼吸のリズムをたどる旅です。
目次
味わう ― 世界を受け取る感性の入口
味わうことは、世界と調和する最初の行為だと思う。
食を通して、空間を通して、ワインを通して、私は「受け取る」という感覚を学び直していた。
一皿の背景にある人や物語。
空間がつくる光や会話の響き。
それらが重なり合う時間の中で、味わいは単なる味覚を超えて「世界の断面」になっていった。
ワインの学びでは、知識と感性、理論と直感のあいだに橋がかかった。
知識を積み上げることは、世界を細やかに感じるための準備だった。
感性を研ぎ澄ませることは、知識を再び生命へと還すことだった。
味わうとは、世界の変化をそのまま受け取ること。
それは「整える」ことの始まりでもあり、内なる発酵の入口でもある。
選ぶ ― 感性が生き方へと展開する
よいものを選ぶという行為は、世界の中から何かを“分ける”ことではなく、世界と“関係を結ぶ”ことだ。
この感覚を掴んだとき、選択という言葉の意味が変わった。
ワインを選ぶとき、それは「どんな時間を味わいたいか」を選ぶことでもある。
器を選ぶとき、それは「どんな空気を纏いたいか」を決めることでもある。
選ぶという行為の中に、未来の景色がすでに含まれている。
よいものを選ぶとは、自分の感性に責任を持つこと。
誰かの評価に寄りかからず、自分の“よさ”を信じて手を伸ばすこと。
その瞬間、世界との関係が一つ深くなる。
選ぶとは、未来への祈りにも似ている。
これからの時間をどう生きたいか。
その問いに、日々の選択が静かに応えている。
驚く ― 感性が再び世界をひらく
驚きは、予定調和の中に突然現れる“風”のようなものだ。
予測できないものに出会うとき、世界は新しく立ち上がる。
「味わう」ことで世界を受け取り、
「選ぶ」ことで世界に応答し、
その先に訪れるのが「驚き」だ。
驚きは、感性が再び開かれる瞬間。
そこでは、知識も計画も一度ほどけ、ただ“感じる”だけになる。
それは、生命が世界と再びつながる呼吸のような出来事だ。
日常の中で小さなズレや偶然に出会うとき、
そこに世界の「新しい入口」が現れる。
驚きを避けず、歓迎する。
それだけで、世界は少しずつ広がっていく。
感性の循環 ― 生きることの呼吸として
味わうとは、受け取ること。
選ぶとは、応答すること。
驚くとは、開くこと。
この三つのリズムが、感性の呼吸をつくっている。
それは学びでもあり、生きることの構造でもある。
内で発酵し、外へ循環し、また内に戻ってくる。
その往復が、私たちの感性を育てていく。
「味わい・選び・驚き」は、世界を感じる三つの軸であり、
それぞれが他の二つを静かに支え合っている。
感じる力、応答する力、そして開く力。
この呼吸の中で、生命は更新されていく。
そして、その呼吸のリズムは、
きっと誰の中にもすでに流れている。
この特集の3本
味わいの構造 ― 食からワインへ、学びの旅路

Appreciate Life through Wine 食からはじまり、空間を経て、ワインへ。 半年の学びのなかで、「味わう」という行為は、 ただの感覚ではなく、世界の構造を映す鏡となっていった。 一皿の背景にある人や物語、 空間がつくる味わいの重なり、 そして、ワインという言...
よいものを選ぶとは、世界の見方を選ぶこと

Appreciate Life through Choice よいものを選ぶというのは、単に品質を見極めることではない。 それは、世界をどのように感じ、どう関わるかという「姿勢」を選ぶ行為でもある。 味わいが感性の行為だとすれば、選択はその感性の延長線上にある。 何を美しいと感じ...
驚きという構造 ― 世界がひらく瞬間
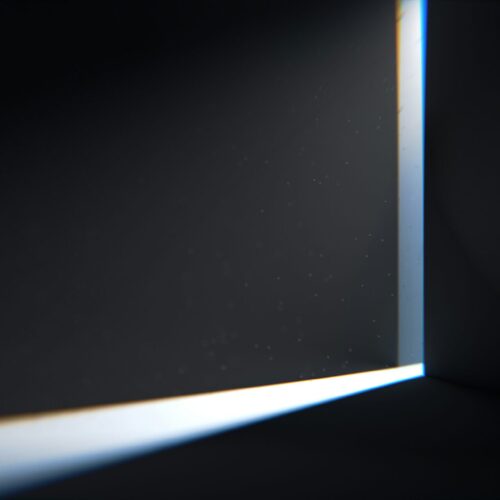
Appreciate Life through Wonder 世界はいつも、私たちの知覚の枠組みの中で見えている。 見慣れた道、聞き慣れた声、繰り返される習慣。 その安定の上に、私たちは世界を“理解した”つもりで立っている。 だが、ある瞬間、予期せぬ出来事や、何気ない風景のなかで、 ...
詩的な感性の面から同テーマを綴ったエッセイも、noteで公開しています。
note「味わい・よいもの・驚き」シリーズ
感性が整うと、実践の質が変わる
受け取る・応答する・ひらくという感性のリズムを、
日々の選択やふるまいの中へ、静かに返していく。