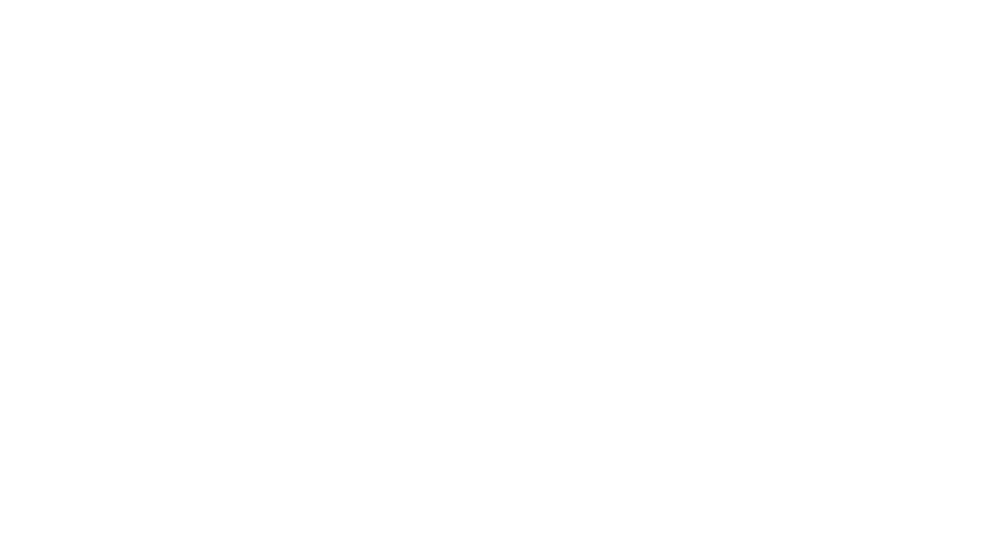「律」とは、揺るがない強さ──そんな印象を持つかもしれません。
でも本当の律は、もっと柔らかく、生きているように揺らぎながら宿るもの。
ぶれながらも、自分に還ってこれる“しなやかさ”にこそ、その本質があるのです。
律とは「ぶれないこと」ではない
「律」と聞くと、何か一本の筋が通った“ぶれない自分”を思い浮かべるかもしれません。けれど、本当の律とは“ぶれない”ことではなく、“ぶれたときにどう戻るか”を含んだ、もっと動的なものだとわたしたちは考えています。
木が風に揺れてもしなやかに立っているように、しなること・揺れることそのものが、生きている証かもしれません。そして、揺れた先で、何を選び、どう戻ってくるのか。そのプロセスにこそ、その人なりの「律」が宿るのです。
律が揺れたときのサインとは?
「いつもよりイライラしやすい」「大切にしていたはずのことに興味が持てない」「なんとなく惰性で過ごしている」──これらは、内側の律が揺れているときのサインかもしれません。
外からの情報や人間関係、体調の変化、社会の動き。私たちは常に多くの影響の中で生きていて、軸が揺れることは自然なことです。大切なのは、その“揺れ”に気づく感性を持っているかどうか。そして、それを否定せずに受け止められるかどうかです。
揺れた自分とどうつきあうか
揺れは悪いものではありません。むしろ、自分が何に反応して、どこに“戻りたくなる”のかを教えてくれる、大切なサインです。
揺れを否定せず、まずは「いま自分は揺れているな」と静かに認める。そして、焦らずに整えていく。その中でこそ、本当の“律”が磨かれていきます。
しなやかな律を育てるための視点
方法は人それぞれですが、たとえば次のような「視点」が役に立ちます。
- 朝の内省: 一日の最初に「どう在りたいか」を自分に訊く。
- 判断の基準: 迷ったら「過去の自分が誇れるか?」で選ぶ。
- 手放しの習慣: しっくりこないものを小さくやめて軽くする。
どれも、“ぶれたら戻る”ための足場を増やす考え方です。
APLF的視点で見る「揺れ」と「律」
APLFでは、「律」は固定された一本の芯ではなく、“しなやかに揺れても、また立ち戻れる構造”として捉えています。
それは、丹田のような身体の中心でもあり、感性と理性の間で揺れる心の重心でもある。ゆれ動きながら、自分自身とのつながりを取り戻していく──そのプロセス全体が、「律を生きる」ということだと私たちは考えています。
まとめと問いかけ
ぶれないことではなく、ぶれても戻ってこれること。
「律」とは、生きているからこそ揺れる、その繊細な感覚を大切にすることです。
今日のあなたに問いかけてみてください。
- 最近、自分の律が揺れた瞬間はありましたか?
- その揺れをどう受け止め、どんな選択をしましたか?
- あなたが戻りたいと思える“原点”は、どこにありますか?