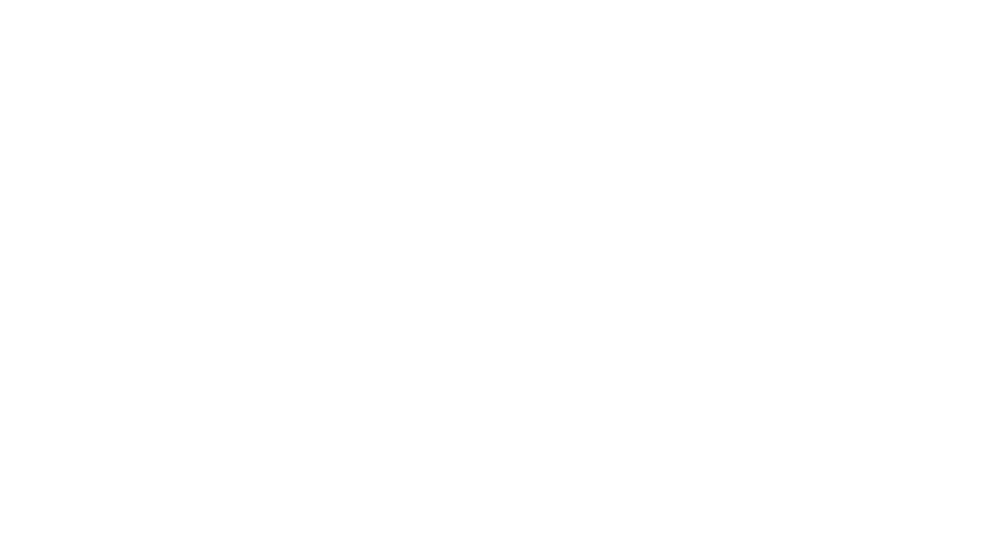よいものを持つこと、よいものに囲まれること。
それは単に高価なものを集めることではなく、
自分にとって本当に価値あるものを選び取る“眼”を育てることです。
この世界には膨大な情報とモノがあふれています。
そんな時代だからこそ、「よいもの」を見分ける力が、
人生の質を左右すると言っても過言ではありません。
「よいもの」とは誰にとっての“よさ”か
“よいもの”とは何でしょうか?
高品質、長持ち、有名、希少、美しい──さまざまな基準がありますが、
それは誰の基準でしょうか。
大切なのは、「自分にとって何がよいのか」という視点。
他人の評価ではなく、自分自身の身体感覚や経験を通じて感じる“よさ”こそ、
本質的な価値と言えるでしょう。
情報があふれる時代の“選び方”とは
レビュー、ランキング、SNS。
それらが参考になる一方で、情報に振り回されると感性が鈍っていきます。
「なぜ自分はこれをよいと思うのか?」
この問いを立てることで、選ぶ力が養われていきます。
経験・対話・背景から“よさ”を感じとる
「よいもの」は、性能だけでなく背景や人との対話、体験の中から立ち上がる。
土の匂い、手仕事のぬくもり、作り手の声。
“よさ”は文脈とともに息づく感覚なのです。
実践のヒント:よいものに出会う3つの姿勢
- 背景を感じ取る。 ものの奥にある人や物語に耳を澄ませてみる。
- 時間を味わう。 長く使うほど、自分との関係が深まっていく。
- 語り合う。 他者の“よさ”の感じ方に触れることで、自分の感性も広がる。
行動というより、選ぶときの“まなざし”を育てる感覚で。
よいものは、探すものではなく、気づくものです。
APLF的視点:命のバトンとしての「よいもの」
APLFでは、“よいもの”を単なる所有物ではなく、
命のバトンとしてとらえます。
自分の時間や感性を託す“媒体”であり、やがて誰かに受け渡されていくもの。
選ぶという行為は、未来への贈り物を選ぶようなものです。
問い
──最近、「これはよい」と心から思えた瞬間はいつでしたか?
値段や流行ではなく、その“感じた理由”を言葉にしてみてください。
日々の中の“よさ”を見つけるまなざし。
それが、これからの豊かさの鍵になるはずです。