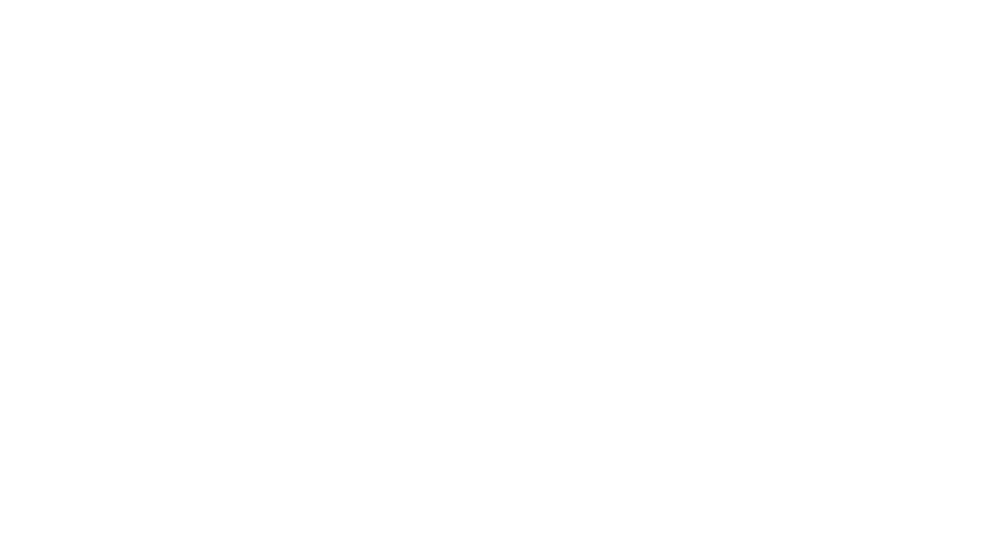Appreciate Life through Wine
食からはじまり、空間を経て、ワインへ。
半年の学びのなかで、「味わう」という行為は、
ただの感覚ではなく、世界の構造を映す鏡となっていった。
一皿の背景にある人や物語、
空間がつくる味わいの重なり、
そして、ワインという言語が教えてくれた“整える力”。
発酵と熟成のあいだで、
知識は静かに感性へと変わり、
学びは人生のリズムそのものになっていく。
これは、一人の探求者が「味わうこと」を通して見つめた、
世界と自分のあいだの物語。
少し長めの文章です。
章ごとに区切りながら、
感性が静かに発酵していくように読んでもらえたら嬉しい。
味わうことが、人生を変える

食べることは、生きることである。
“味わうこと”は、生き方を変える。
味わうことは、生きるために“必要ではない”からこそ、生きることを豊かにする。
この三年間、私は「食」という日常的な行為のなかに、
世界の構造や人とのつながり、そして自分の在り方を見つめてきた。
2023年、グルメ会を通じて出会った人たちは、
単に料理を楽しむのではなく、
経営やプロデュース、発信の視点で“食の世界”を再構築していた。
食を“ビジネス”としてではなく、価値の交換として見つめること。
そこに私は、社会や人の動きが凝縮された一枚の皿を感じた。
2024年、Zaimokuza Namiとの出会いによって、
食の体験はさらなる“空間と人の共鳴”へと拡張していった。
一皿の物語、生産者と料理人、そして食べ手。
その交わりの中で、味わいは単なる味覚を超え、
時間と関係の芸術へと変わっていった。
そして2025年、ワインという新しい言語に出会う。
もちろん、ワインという単語は知っていた。
それが、単なる飲み物ではなく、
一つの言語、一つの思考体系として立ち上がっていった。
その世界では、知識と感性、記憶と直感が複雑に絡み合い、
「味わうこと」がまるで思考のように展開していく。
縁と勢いに導かれて受けた試験という枠組みの中で、
私は“味わうこと”の裏にある、構造の美しさを見た。
食という入口 ― 価値の交換としての一皿

2023年、グルメの場で出会った人々を通して、
「食」が人と世界をつなぐ“価値の交換”であることに気づく。
一皿の背景には、人と物語、そして小さな循環の気配が息づいていた。
⸻
思い返せば、食への興味はずっと前からあった。
小学生の頃に夢中で読んでいた料理漫画、
出張先で偶然入った店の味、
どれも心に残っている。
ただ、当時のそれは“点”のような体験だった。
一つひとつの味は鮮明でも、
まだ世界や人とのつながりの中で捉えることはなかった。
それが2023年、グルメ会や食の発信者たちとの出会いによって、
点が線となり、面になり、やがて立体的な構造を帯びていった。
食は、味覚の世界で完結するものではなく、
経営・デザイン・発信・人間関係──
それらすべてが交わるひとつのネットワークだと感じた。
⸻
私が惹かれたのは、料理そのものよりも、その構造だった。
一皿が生まれる背景には、素材を届ける人、料理人、
それを伝える人、そして受け取る人がいる。
その関係の重なり方にこそ、「美味しさの本体」があるように思えた。
彼らの活動を通して、
食が単なる娯楽や情報ではなく、価値の交換として機能していることを知った。
一皿が生む感動の裏には、
それを支える見えない仕組みと、誠実な意図がある。
その構造を感じ取ることで、
私の中の「味わう」という行為も変わっていった。
感覚の点が、意識の線とつながり、
やがて面となって世界を立体的に映し出す。
まるでワインの学びで、
飲んでいたものが“言語”へと変わっていった過程を先取りしていたようだった。
⸻
この年の経験は、
食を「味」ではなく「関係性」として捉えるきっかけになった。
料理を食べるとは、誰かの想いを受け取ること。
その想いを感じ取る感性が、
さらに次の価値交換を生み出していく。
そしてその流れは、翌年のZaimokuza Namiとの出会いへとつながり、
「場」そのものを味わうという、新しい段階へ向かっていった。
空間という体験装置 ― 物語を味わうということ

食の体験が、空間や人の関係性へと広がっていく。
Namiでの時間を通じて、味わいは点から面へ、そして立体へ。
物語を味わうとは、世界の呼吸に耳を澄ますことだった。
⸻
2024年、Zaimokuza Namiとの出会いが訪れた。
そのきっかけは、Instagramの投稿だった。
たまたま目に留まった美しい料理の写真。
完全予約制、抽選でしか入れないと知り、
どこか遠い存在のように感じていた。
けれど、ある日「メンバーシップ募集」の投稿を見つけ、思い切って応募した。
メンバーシップは、単に予約が取りやすくなる制度ではなかった。
料理教室や特別な企画などを通じて、
Namiという空間に連続的に関わることができる“縁”のようなものだった。
その連続性が、私にとって新しかった。
食を「点」として味わうのではなく、
人と時間のつながりの中で「面」として感じる。
味わいが、関係性の中で立体的に変化していく。
目の前の一皿に、静かに息づく「物語」を感じた。
生産者の想い、料理人の意図、
そしてその場に居合わせた人々の会話。
それらが一瞬ごとに交差し、
食事というよりも、ひとつの演奏会のように響いていた。
⸻
Namiでは、料理の味だけでなく、空間そのものが味わいをつくっていた。
光の加減、器の質感、音の響き、会話の間(ま)。
そのすべてが一体となり、味覚の印象を変えていく。
一皿の味は、素材や技術だけでは決まらない。
同じ料理でも、光が少し変われば余韻も変わる。
隣の人との対話や、静かな間の取り方によって、
甘みや香りの立ち上がり方まで違って感じることがある。
味わいは、舌や鼻だけで感じるものではなく、
空間と時間の関係性として現れる現象なのだと思った。
その日の空気、その場にいる人、季節の光。
それらすべてが一瞬の共鳴を生み、
その“いま”を閉じ込めた一皿が完成する。
だからこそ、同じメニューでも、同じ夜は二度と訪れない。
食事は「再現」ではなく、「生成」の出来事。
その場に流れる生命のリズムの中で、
私たちはただ、味わいの変化を受け取っている。
その感覚は、後にワインのテイスティングで感じた
“同じボトルでも日ごとに味が変わる”という現象にも通じていた。
味わいは固定されたものではなく、
関係の中で生まれ、関係の中で消えていくものなのだ。
⸻
Namiという小さな空間では、
休日喫茶室や季節の企画、
そして“ものがたり食堂”など、
いくつもの表現が交わりながら展開されている。
Namiは、日常の空間の中で、
物語を静かに息づかせる場だった。
一皿には、物語の断片が宿り、
光や会話の余白のなかで、
食と人と時間がゆるやかに共鳴していた。
“物語を味わう”ということは、
物語の登場人物になることではなく、
その世界の呼吸を、自分の中に通すこと。
食という最も身近で生命的な行為のなかに、
想像と現実が重なり合う瞬間がある。
その感覚が、私の中で「味わう」という言葉の意味を
さらに深いものへと変えていった。
ワインという言語 ― 知と感性の統合

勢いで踏み込んだワインの世界。
知識と感性、理論と直感が交わり、味わうことが思考になる。
学びと体験のあいだで、「感じる」と「考える」の統合が始まった。
ワインという新しい言語
2025年、ワインの世界へ踏み込んだ。
きっかけは明確な計画ではなく、
いくつかの縁と、少しの勢いだった。
それでも、一度その扉を開くと、
その世界は想像以上に深く、広く、
そして「食」とはまったく違う座標軸を持っていた。
これまで“ただ飲んでいた”ワインが、
ある日突然、言語のように感じられる瞬間があった。
そこには文法があり、語彙があり、
香りや味わいが「意味」を持って語りかけてくる。
それは、世界の文化や気候、土地の記憶が凝縮された“液体の記号”だった。
ワインを学ぶということは、
その記号体系を読み解き、語り返すことに近い。
ただ味わうことから、理解して味わうことへ。
感性と知識のあいだに橋がかかるような感覚だった。
この一年、ワインを通じて私は、
味わうという行為が「思考」と「存在」を結ぶものだと知った。
一次試験 ― 知識の地図を描く
一次試験の勉強は、想像以上に広く、そして深かった。
覚える量の多さに圧倒されながらも、
世界中のワイン産地を学ぶうちに、
それまで点でしかなかった味の記憶が、
ゆっくりと地図のように繋がっていくのを感じた。
産地、気候、土壌、文化──
それらが味わいを形づくる“背景”として整理されていく。
そしてある瞬間、ラベルに書かれた文字が、
ただの情報ではなく、物語の入口に変わる。
机上の知識を覚えることが、
こんなにも感覚を豊かにするとは思わなかった。
学ぶほどに、過去に飲んだワインの香りや質感が、
記憶の底から立ち上がってくる。
知識が感性を開き、感性が知識を呼び覚ます。
その循環の中で、私は“理解して味わう”という静かな快楽を知った。
一次試験の合格の文字を見たとき、
それは単なる通過点というより、
世界の構造が一枚の地図として手の中に現れたような感覚だった。
二次試験 ― 感覚と理論の統合
二次試験の勉強は、一次までの“知識の積み上げ”とはまるで違った。
一次を通過できると思っていなかったこともあり、
準備期間はわずか一か月。
だからこそ、限られた時間の中で感覚を研ぎ澄ませていった。
自宅やワインバーでの練習を重ねるうちに、
ただ香りを取るのではなく、感覚を整えるという意識に変わっていった。
グラスの中にあるのは液体ではなく、時間だった。
開けた瞬間から表情が変わり、
温度や空気が味わいを少しずつ書き換えていく。
その変化を観察するうちに、
ワインを「分析する」よりも、「聴く」ような感覚になっていった。
練習を重ねるほど、
香りや味の要素を言葉に置き換える難しさと、
言葉を通じてしか見えない領域の両方を感じた。
知識を頼りにすると思考が固くなり、
感覚に任せると根拠が消える。
そのあいだで揺れる自分を、ただ観察するようになった。
日によって集中力も体調も違う。
舌の感度も変わる。
だからこそ、「整える」ことの意味が深まっていった。
香水をつけない、食事を軽くする、
余計な雑念を減らす──
それらがすべて“味わうための準備”だった。
試験本番は一瞬だった。
品種も、産地も、ヴィンテージも外した。
それでも、コメントの方向性は合っていた。
正解を当てることも、もちろん大切だ。
その精度を追う中で、感覚と論理が磨かれていく。
だが同時に、
自分の感覚を信じて整えることの方も、
それに劣らず大切だと感じた。
感じることと考えること、
その間(ま)にある沈黙が、
味わいの本質をそっと教えてくれていた。
言語化の先にある沈黙
勉強を終えてしばらく経った今でも、
グラスを前にすると、少しだけ緊張する。
それは、当てるための緊張ではなく、
目の前のワインが何を語ろうとしているのかを、
受け取ろうとする静かな集中だ。
この一年を通じて、
「味わう」とは、感じることでも、理解することでもなく、
その両方のあいだにある“間(ま)”に立つことだと感じた。
言葉を学び、理論を積み上げ、
それでも最後は、沈黙の中にすべてが還っていく。
感覚は記憶となり、
記憶はまた次の感覚を呼び起こす。
そうしてワインは、
ひとつの試験を超えて、
自分の内側で静かに熟成していく。
正解や不正解という枠を離れたとき、
そこに残るのは「感じ取る力」そのものだ。
それは理屈ではなく、
生命のリズムに近い。
いま、グラスの中の液体を見つめながら思う。
学びは終わらない。
それは常に発酵しつづけるものであり、
沈黙の中で、静かに新しい香りを生み出している。
発酵と熟成のあいだで

試験を終えても、学びは静かに続いている。
内で発酵し、外へと循環しながら、人生そのものが熟していく。
終わりではなく、呼吸のように続く旅の途中で。
熟成とは終わりではなく、続く発酵
二次試験が終わってから、少し時間が経った。
結果は残念だったが、不思議と悔しさはなかった。
今年の受験を通して感じていたのは、
焦りや緊張ではなく、静かな集中だった。
それは、終わりというより、
まだ“発酵の途中”にいるような感覚だった。
この半年は、仕込みと発酵の時間だったと思う。
知識や感覚を混ぜ合わせ、
日々の練習や体験を通して、
少しずつ自分の中の構造が変わっていった。
勉強は、これからも続いていく。
来年、もう一度この世界に挑む。
けれど、より落ち着いた呼吸で、
熟成のように“静かに育てていく学び方”をしていきたいと思う。
発酵と熟成のあいだには、明確な境界がない。
動きながら落ち着き、
落ち着きながら動き続ける。
学びもまた、そういうものだ。
結果という形を超えて、
内側で静かに進み続けている。
そしてそれは、
自分の生き方そのものを少しずつ変えていく、
穏やかな力として、静かに息づいていく。
内なる発酵 ― 見えない変化が進む
何かを学ぶとき、
最初は理解しようと努力する。
構造を覚え、理屈を掴み、整理する。
けれど、時間が経つと、
その知識は少しずつ形を失っていく。
忘れてしまったようにも思える。
それでも、ふとした瞬間に、
以前とは違う感覚で世界を見ている自分に気づく。
学びは、表面から消えても、
内側では発酵のように進んでいるのだと思う。
新しい情報や体験が加わるたびに、
それまでの理解が静かに書き換えられていく。
明確なアウトプットがなくても、
感性や判断の“基準”が少しずつ変わっていく。
それは、意識的な努力というより、
無意識の働きに近い。
ひとつの経験が、別の領域に滲み出し、
思考や行動の質を少しずつ変えていく。
発酵とは、変化の途中にある安定だ。
外からは見えなくても、
内側では複雑な反応が続いている。
学びもまた同じ。
すぐに成果として現れなくても、
その沈黙の中で、
次の段階への準備が着実に進んでいる。
外への循環 ― 味わいを他者に渡す
内側で熟していくものは、
いつか外へとにじみ出ていく。
学びや気づきを誰かに話したり、
一緒にワインを飲んだりするたびに、
自分の中にあったものが再び動き始めるのを感じる。
それは、教えることや発信とは少し違う。
どちらかといえば、共鳴に近い。
こちらが味わい、相手も味わう。
そのあいだに生まれる空気が、
さらに新しい理解を生んでいく。
話すことで整理され、
聞かれることで形を変え、
そのたびに自分の中の学びが“再発酵”していく。
ワインの世界でも同じだ。
ボトルを開け、グラスに注ぎ、
空気と触れ合うことで味わいが変化する。
その変化を、誰かと分かち合うことで、
体験は単なる味覚ではなく、関係の記憶に変わっていく。
学びもまた、閉じたままでは熟成しない。
誰かに渡すことで、
新しい空気を取り込み、再び動き出す。
その循環の中で、
自分という容器の形も少しずつ変わっていく。
ワインが時間と共に育つように、
人もまた、関わりの中で発酵と熟成を繰り返している。
静かな余韻の中で
気づけば、ワインを学び始めてから半年が経っていた。
振り返ればあっという間でありながら、
その中には、季節がいくつも通り過ぎたような濃密さがあった。
この半年で手にしたものの多くは、
目に見える成果ではなく、
静かに沈んでいくような感覚だった。
けれど、それこそが本当の学びなのかもしれない。
ワインを通じて感じたのは、
味わいとは「一瞬」ではなく、流れの中にあるということ。
香りが立ち上がり、温度が変わり、
空気や人との関係の中で表情を変えていく。
その変化を受け入れることが、
味わうということの本質なのだと思う。
人生もまた同じだ。
予測できない変化を抱えながら、
その都度、整え、味わい、また次へと進んでいく。
それは、終わりのない発酵と熟成の循環。
これからまた、新しい季節が始まる。
まだ知らない味、まだ出会っていない人、
そして、まだ言葉にならない感覚。
そのすべてを、静かな呼吸のように味わいながら、
次のグラスを、ゆっくりと傾けていこうと思う。
食も、空間も、ワインも、
すべては「生きること」を深く感じるための入口だった。
これからも、日常の中で静かに発酵を続けながら、
次の一杯、次の出会いを味わっていきたい。
今日の余韻が、また新しい季節を育てていく。
関連:よいものを選ぶとは、世界の見方を選ぶこと
「味わう」ことで開かれた感性は、やがて「選ぶ」という行為へと向かっていく。
次の記事では、感性がどのように価値判断へと展開していくかを見つめている。

Appreciate Life through Choice よいものを選ぶというのは、単に品質を見極めることではない。 それは、世界をどのように感じ、どう関わるかという「姿勢」を選ぶ行為でもある。 味わいが感性の行為だとすれば、選択はその感性の延長線上にある。 何を美しいと感じ...
関連:驚きという構造 ― 世界がひらく瞬間
味わいと選択の先で、世界はふと、予期せぬかたちでひらかれる。
その瞬間に起こる「驚き」の構造を、次の記事で探っている。
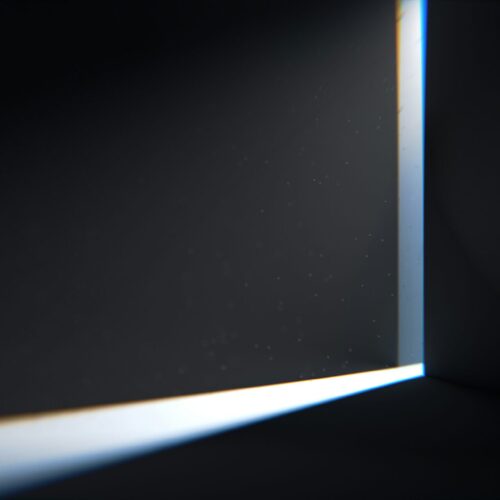
Appreciate Life through Wonder 世界はいつも、私たちの知覚の枠組みの中で見えている。 見慣れた道、聞き慣れた声、繰り返される習慣。 その安定の上に、私たちは世界を“理解した”つもりで立っている。 だが、ある瞬間、予期せぬ出来事や、何気ない風景のなかで、 ...
詩的な感性の面から同テーマを綴ったエッセイも、noteで公開しています。
note「味わいの余韻の中で ― 半年のワインと、静かな発酵」